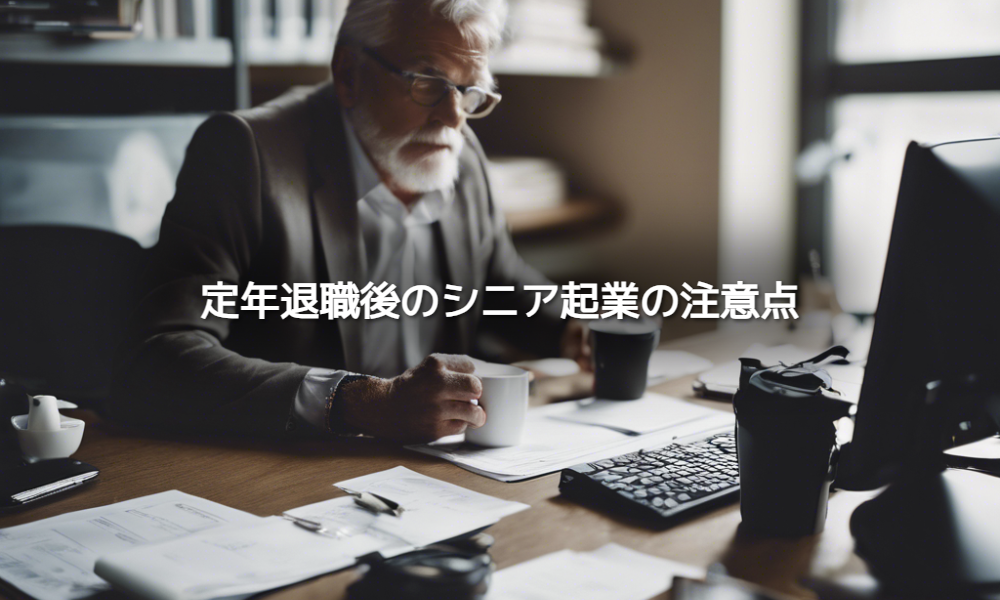定年退職後のシニア起業の注意点
- 投稿日:
- 更新日:
「人生100年時代」と言われる中、定年を迎えた後も人生はまだまだ長く、年金だけでは不安と感じる方も多いのではないでしょうか。一方で、「自分のペースで働き続けたい」「経験を活かしてまだ社会とつながっていたい」という思いを抱く方もいます。
実際、日本では65歳以上の就業者数が2023年に914万人に達し、20年連続で増加、過去最多となりました。これは15歳以上の就業者の約13.5%、つまり働く人の7人に1人が65歳以上に当たります(総務省統計局)。さらに、労働政策研究・研修機構(JIL)の基調報告によれば、過去10年間で60歳以上の就業者は約20%増加し、「70~74歳」で60.3%、「75歳以上」で76.7%という顕著な伸びも記録されています(JIL基調報告)。
つまり、定年後もしっかり働きたい――そう考えるシニア世代が増えているのは紛れもない事実。そのため、「もう一度、自分らしい形で収入を得たい」といったニーズは、個人的な希望というより社会的トレンドとも言えます。
とはいえ、その一歩を踏み出すには、年金とのバランス、働き方の形態、資金計画、健康の確保など、多くの考慮点があります。この記事では、定年後の起業や働き方を安心して始めるために、今知っておきたい注意点をわかりやすく整理しました。
なぜ定年退職後の会社設立・起業が注目されているのか?
ここ数年、定年を迎えた後に会社を設立したり、個人事業を始めるシニアが増えています。単なる一時的なブームではなく、社会全体の流れとして定着しつつあるのです。その背景には、いくつかの事情があります。
まず大きいのは「働き続ける高齢者の増加」です。総務省の統計によれば、65歳以上の就業者は2023年に914万人となり、20年連続で増加しています。今や働く人の7人に1人が65歳以上という時代です。ところが一方で、求人の受け皿はむしろ縮小しています。労働政策研究・研修機構(JIL)の調査では、「60歳以上歓迎」と明示した求人は2020年をピークに、その後は4割ほどまで減少しました。
では、なぜ求人が減っているのでしょうか。理由はいくつか考えられます。
- 人手不足の業種構造の変化
コロナ禍を経て人手不足は続いていますが、求められているのは配送・介護・建設など体力を要する現場が多く、シニア層には厳しい職種が目立ちます。 - 企業の求人表記の変化
かつては「60歳以上歓迎」と年齢を前面に出した募集がありましたが、年齢差別を避ける意識が強まり、表現を控える企業が増えました。そのため求人票上では減って見えるものの、実際は応募できる余地がある場合もあります。 - 雇用コストとリスク回避
高齢者を雇う場合、労災や健康面への配慮が必要になり、企業にとってはリスクも伴います。そのため、定期的に雇用契約を更新する「継続雇用」より、短期契約や業務委託で対応する傾向が強まっています。
こうした事情から、「働きたい人は増えているのに、雇用の受け皿が狭まっている」というギャップが生まれています。だからこそ、定年後も働き続けたいと考える人にとっては、起業という選択肢が現実味を帯びてきているのです。
起業であれば、これまでの経験や人脈を生かしながら、自分の体力や生活リズムに合わせた働き方を組み立てられます。「人生100年時代、年金だけでは心もとない」という不安を埋める手段としても注目されるのは当然といえるでしょう。
法人か個人事業主、どちらで起業するか?
定年後に事業を始めるとき、最初に立ちはだかるのが「法人にするか」「個人事業主で始めるか」という選択です。どちらが正解というわけではなく、自分のやりたいことや状況に合わせて考えるのが大切です。
法人を選ぶと安心できるケース
- 取引先から法人格を求められる場合
自治体や大手企業との契約は、ほとんどが法人であることを条件にしています。これまでのキャリアを活かして大きな取引に関わりたい方は、法人を選ぶほうが道が開けやすいでしょう。 - 今後、事業を広げる可能性がある場合
もし売上が数百万円から数千万円規模へと育つ見込みがあるなら、法人化したほうが税金や資金調達の面で有利になることがあります。
「せっかく起業するなら信用力を大切にしたい」「取引先と肩を並べたい」と感じる方は、法人を前提に考えてみると安心です。
個人事業主を選んだほうがよいケース
- 売上がまだ見込めない、または小さい場合
事業を始めたばかりで先行きが読めないときに、法人の設立費用や毎年の決算コストを背負うのはリスクが大きいです。小さく始めるなら、個人事業主として低コストで試すのが現実的です。 - まずは“お試し”でやってみたい場合
「本当に自分に合っているか分からない」「趣味を仕事にできるか挑戦してみたい」といった気持ちなら、まずは個人事業主で様子を見るほうが安心です。
「身の丈に合った形で、失敗しても痛手を最小限にしたい」と考える方は、個人事業主からスタートするのが合っているかもしれません。
判断のための考え方
最終的には「自分がどんな働き方を望んでいるか」で答えが変わります。
- 信用を得て大きな取引をしたいのか?
- それとも、生活費の足しになる程度で十分なのか?
- 体力や気力をどれくらい事業に注ぎ込めそうか?
こうした問いを自分に投げかけてみると、どちらが自分に合っているか自然と見えてきます。もし迷うようなら、専門家に相談してシミュレーションしてみるのも一つの方法です。
定年退職後のシニア起業は年金も気をつけたい
【法人か個人事業主どちらで起業をするか】
法人か個人事業主どちらで起業をするかについて、社会的な信用や責任を負う範囲、税制上の違いなどを考慮して 判断をしていく必要がございます。どちらが良いか判断が難しい場合、専門家に相談することをおすすめします。
シニア起業の場合は、上記のことに加えて年金についても考慮する必要がございます。
定年後に働くと年金が減るという話を聞いたことがあるかもしれませんが、
年金が減る可能性がある場合は下記の条件に該当する場合になります。
・年金受給開始後も厚生年金保険の被保険者として働いている場合
・総報酬月額相当と老齢厚生年金の合計が50万円を超えている場合
法人として起業をする場合は、基本的に厚生年金保険に加入するため、
月額の役員報酬と老齢厚生年金の合計が50万円を超える場合には、超えた金額に応じて
一部年金が受給停止になります。
一方、個人事業主として起業する場合は基本的に厚生年金保険に加入できない為、
年金の受給額が減ることはなく満額受給できます。
しかし、厚生年金保険に加入しない分、将来の老齢厚生年金を増やすことができません。
健康面
起業は心身ともに大きな負担がかかります。心身ともに健康でいることは、事業を成功させるためにも重要です。
病気にかかってしまうと事業を継続することができなくなります。
定期的な健康診断等、健康リスクについても備えましょう。
起業後、休みなく働かれる方もいらっしゃいますが、体の健康や心の健康のためにも休息をしっかりとることは重要です。